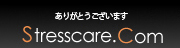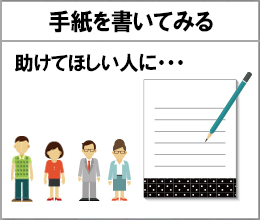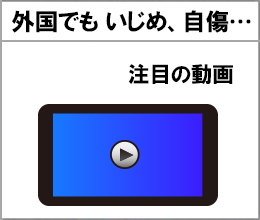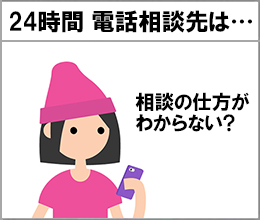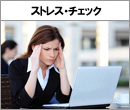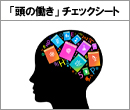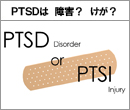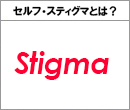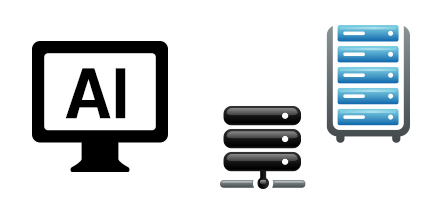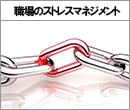|
『研修のひろば』(特別区職員研修所2004年3月12日発行)
の掲載原稿(P15~P18)より一部抜粋
|

■ ワークライフバランスはタイムチェックから
■ ワークライフバランスとストレス度には密接な関係がある
■ タイム・マネジメントとスキルアップを活用する
■ 「短期的なワークライフバランス」と「長期的なワークライフバランス」を考える
■ ワークライフバランスとストレス度には密接な関係がある
■ タイム・マネジメントとスキルアップを活用する
■ 「短期的なワークライフバランス」と「長期的なワークライフバランス」を考える
[用語解説] ワーク・ライフ・バランス
「ワーク・ライフ・バランス」とは、仕事と生活のバランスをとろうという考え方で、米国では古くからある考え方。90年代後半に米企業で盛んに取り入れられるようになった。古くは、「ワーク・ファミリー・バランス」と呼ばれ、社会進出した女性が家庭とのバランスをとりやすくするための施策であったが、90年代後半からは、米国経済が好調だったことから、リテンション(人材定着)を目的として、導入する企業が増えた。
ただ、米国で最も尊敬される経営者の一人であるGEのジャック・ウェルチ元会長は、「国際競争が厳しくなっている中で、豊かになるためなら徹底的に働くという労働者の多い新興国との競争に本当に勝てるのか」という視点から「ワーク・ライフ・バランス」に対して懐疑的であった。
その一方で、米国海軍は、「ワーク・ライフ・バランス」が重要であり、特に「ライフ」が重要であるという視点から、「ライフ」を先に呼称する「ライフ・ワーク・バランス」という呼び方を行い、「タスク・フォース・ライフ・ワーク(TFLW)」を始めている。これは、優秀なリーダーを獲得するための施策である。
近年日本でも「ワーク・ライフ・バランス」の重要性が指摘されるようになり、官民あげた取り組みが始まっており、内閣府は「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」を発表している。
「ワーク・ライフ・バランス」とは、仕事と生活のバランスをとろうという考え方で、米国では古くからある考え方。90年代後半に米企業で盛んに取り入れられるようになった。古くは、「ワーク・ファミリー・バランス」と呼ばれ、社会進出した女性が家庭とのバランスをとりやすくするための施策であったが、90年代後半からは、米国経済が好調だったことから、リテンション(人材定着)を目的として、導入する企業が増えた。
ただ、米国で最も尊敬される経営者の一人であるGEのジャック・ウェルチ元会長は、「国際競争が厳しくなっている中で、豊かになるためなら徹底的に働くという労働者の多い新興国との競争に本当に勝てるのか」という視点から「ワーク・ライフ・バランス」に対して懐疑的であった。
その一方で、米国海軍は、「ワーク・ライフ・バランス」が重要であり、特に「ライフ」が重要であるという視点から、「ライフ」を先に呼称する「ライフ・ワーク・バランス」という呼び方を行い、「タスク・フォース・ライフ・ワーク(TFLW)」を始めている。これは、優秀なリーダーを獲得するための施策である。
近年日本でも「ワーク・ライフ・バランス」の重要性が指摘されるようになり、官民あげた取り組みが始まっており、内閣府は「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」を発表している。
ワークライフバランスはタイムチェックから
ワークライフバランスというのは、本質的には個人の「心」の問題であり、主観的な要素が非常に強い。人それぞれ、何を「ワーク」と考え、何を「ライフ」と考えるのかという点もまちまちである。
したがって、これらを客観的に判断する指標はないが、強いてあげれば「時間の配分」という点に着目することによって、自分のワークライフバランスが乱れていないかどうかをある程度評価することができる。
まず、自分が「ワーク」及び「ライフ」と考えるものを想定してみる。ほとんどの人の場合、職場での仕事は「ワーク」に含まれるだろう。が、職場以外での仕事を「ワーク」と見るかそうでないかは、人によって考え方が違う。家事労働を「ワーク」と考える人もいるし、「ライフ」と考える人もいる。地域での仕事を「ワーク」と考える人もいるし、「ライフ」と考える人もいるだろう。どちらに入るかを決めるのは、本人の全くの自由だ。
こうして決めた「ワーク」と「ライフ」に分けて自分の生活時間を振り返ってみると、自分のワークライフバランスが見えてくる。
さらにもう一つ必要なことは、自分が望んでいるワークライフバランスを明確にすることだ。「望んでいるバランス」と「現実のバランス」が大幅に乖離していないかどうかを「タイムチェック」してみることが、ワークライフバランスを整えるための出発点だ。
ワークライフバランスとストレス度には密接な関係がある
この時間という観点から見たワークライフバランスとストレス度には、密接な関係がある。私どもが6500名(原稿執筆時点)のデータを調査したところ、現実のワークライフバランスと自分の望んでいるバランスがズレている人ほど、ストレス度が高いという結果が出ている。
一般的には「仕事時間が長い人ほどストレス度が高い」と思われているが、実際には、「仕事時間の長さ」よりも、「自分が望んでいるバランスとの差」のほうがストレスとの相関度は高い。たとえば、同じ「ワーク7:ライフ3」という時間の使い方をしている人でも、仕事と生活を5対5にしたい人にとっては大きなストレスになるが、働くことが好きな人にとってはあまりストレスにはならない。
つまり、ワークライフバランスにおいては、誰にでも当てはまる一律の基準はないということだ。自分が望むのであれば、「ワーク3:ライフ7」でも「ワーク7:ライフ3」でもかまわない。自分に適したバランスに少しでも近づくようにすることがポイントだ。
ちなみに、前述の6500名のデータを平均すると、「ワーク48:ライフ52」のバランスを望んでいるのに対して、現実のバランスは「ワーク65:ライフ35」で、仕事時間が過剰な状態にある人が多いようだ。
タイム・マネジメントとスキルアップを活用する
ワークライフバランスとストレス度に密接な関係がある以上、ワークライフバランスを整えること自体が、有効なストレス・マネジメント対策になると考えられる。
ストレス・マネジメントの基本的な考え方は「コントロールできるものをコントロールすること」だ。組織全体に関わることや、他人のことは、自分ではコントロールできないので、自分でコントロールできるものを変えていくのが現実的な方法と言える。
具体的には二つの方法がある。一つは、「タイム・マネジメント」。もう一つは、仕事の「スキルアップ」だ。
タイム・マネジメントの方法にはいろいろあるが、一つだけおすすめするとすれば、「意識的に休息時間を入れること」である。休息を入れずにダラダラと仕事を続けるよりも、休息を入れてしっかりと休み、休息後の仕事の効率を高めたほうが結果的に仕事時間が短くなる。
ところで、若い人のストレス相談をしていると、「仕事時間が長い」という訴えの背後に、「仕事自体がおもしろくない」という要素が隠れていることが多い。こういう人たちは、いくら仕事時間を減らしても、体感する仕事時間は短くならない。したがって、「タイム・マネジメント」よりも、むしろ、仕事を充実させる方法や、仕事を楽にこなす方法を考えることのほうが必要になる。
それには、「スキルアップ」を図り、仕事を要領よくこなす仕事術を身につけるのがいいだろう。スキルが高まれば、仕事の効率も上がり、時間的にも精神的にも余裕が出てくる。
「短期的なワークライフバランス」と「長期的なワークライフバランス」を考える
スキルアップを図るためには、ある程度自分の時間を犠牲にしてスキルへの投資をすることも必要だ。しばらくの間は、ワークライフバランスが大幅に仕事重視に傾くが、スキルが高まった後には、仕事に余裕が持て、ライフの時間も確保しやすくなる。現在のワークライフバランスよりも、将来のワークライフバランスを良くする戦略だ。
自分が「もう限界だ」と思うほどバランスが崩れてはまずいが、そうでなければ一時的には多少のバランスの悪さがあってもいい。
目先のワークライフバランスにこだわるよりも、ライフスタイル全体を見渡して、「人生トータルでワークライフバランスをとろう」というくらいの気楽な気持ちで取り組んだほうが、結果的にうまくいきやすい。